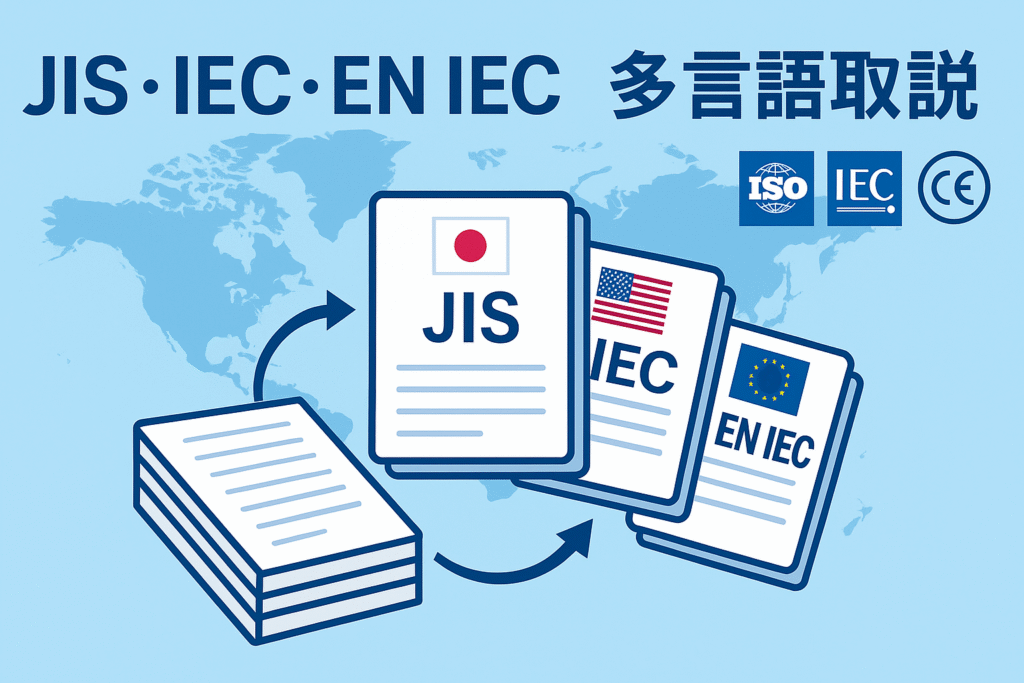
JIS/IEC/EN IECに準拠した多言語展開取説の「現実的」制作フロー
JIS、IEC、EN IECの違いについて
まずそれぞれの規格の違いについておさらいします。
| 規格 | 説明 |
|---|---|
| JIS | 日本の国家規格です。多くはISO/IECの規格を翻訳・微修正したもので、電源電圧・単位・安全マーク寸法など日本特有の条件を盛り込みます。国際規格より数年遅れて整備されることが多いです。 |
| IEC | 国際電気標準化機関です。電気電子分野の規格を策定し、各国が翻訳採用して国家規格や法令へ組み込みます。規格は番号+エディションで管理され、製造者が世界共通の設計指標として利用可能です。 |
| EN IEC | 基本的にはIECと同じですが、EU用の前書きや付属書を追加したり、場合によっては軽微修正したものです。 |
取扱説明書の規格に関して言えば、例えばIEC/IEEE 82079-1 が「情報のつくり方」まで規定しているのに対し、日本側では JIS S 0137 がほぼ同じ骨格を持ちながら、用語や章立て順を日本の慣例に合わせています。
つまり「国際共通の設計コア=IEC、国内向けの化粧直し=JIS」という関係にあります。
制作フローの全体像
現場で扱う資料もレビュー担当者も日本語が中心という前提で、次の順番で進めると手戻りが少なくなります。
- IEC 82079-1に完全準拠した日本語原稿を完成させる。
- 国内法令やJISの細目を追加し、日本向け最終版に仕上げる。
- 完成した日本語版を起点に各言語へ翻訳し、EUでは EN IEC の差分を最後に確認する。
ステップ 1 IEC 82079-1 を骨格に日本語原稿を作成
最初に行うのは、IEC 82079-1の章構成をそのまま使って日本語の本文を組み立てる作業です。見出し番号も条番号も IEC 原文どおりに置いておくと、あとで翻訳支援ツールに読み込んだ際に各言語へズレなく置換できます。安全シンボルは ISO 7010の図記号を配置し、日本語の注意語(危険・警告・注意)には JIS Z 8051 の定義を充てると国内外の用語ブレを防げます。
ステップ 2 国内要件を追加して日本向け完成版に
日本語IEC版がひととおりできたら、次にPSE省令や JIS S 0137が求める細目を差し込んでいきます。
たとえば電源表記を AC100V 50/60Hzに統一する、PSE マークの最小径を確保する、章立て順を「警告→使用制限→据付→操作→保守」に微調整する――といった作業です。
こうして仕上がったファイルが日本出荷用の最終版となり、社内審査や印刷工程に直接渡せます。
ステップ 3 日本語版を翻訳ハブにして多言語展開
日本向け最終版が確定したら、まず英語へ翻訳展開します。
次に、完成した英語版をハブとして、スペイン語やフランス語など追加のローカライズを枝分かれ式に進めます。
EU へ出荷する場合は、翻訳が終わった段階で EN IEC の版表示を確認します。本文がIECと完全一致ならそのまま、軽微修正がある場合はAnnex ZZ(IECにはない欧州専用の附属書)を参照し、該当条文だけ書き換えれば対応完了です。最後にCEマーク、製造年、DoC(適合宣言書)の所在 URL を本文か奥付に追記し、EU向け版が完成します。
まとめ
取扱説明書を効率よく多言語化するコツは、「国際規格としてのIECを日本語で先に固め、国内要件を上乗せし、そこから翻訳する」という制作フローをつくることです。
こうすれば初版段階でIECへの適合が担保され、JIS も EN IEC も”差分”として整理できるため、改訂や市場拡大のたびに大規模な組み直しをする必要がなくなります。
結果として、国内外のユーザーに同じレベルの安全情報を届けつつ、制作コストとリードタイムを最小限に抑えることが可能になります。
\当サービスでは、低コストで高品質なAI時代の取扱説明書作成サービスを提供しています。/
