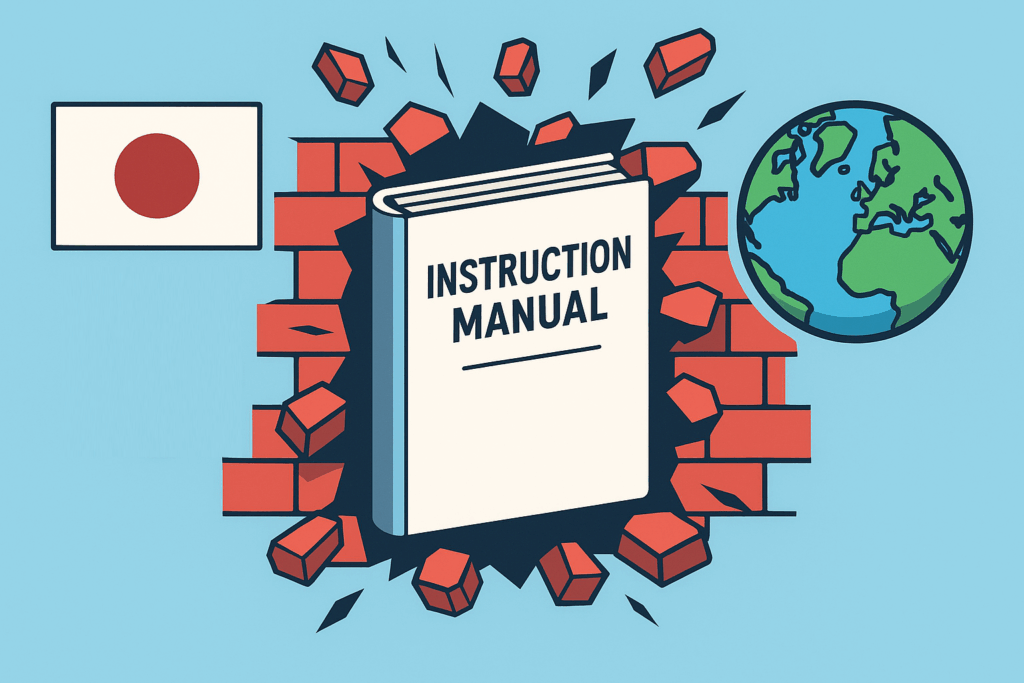
海外輸出におけるCEマーキング・UL認証取説の対応方法
「日本の優れた製品を、世界中の人に届けたい!」と海外市場への挑戦を考えている経営者様、ご担当者様も多いのではないでしょうか。
人口減少が進む日本から海外に活路を見出すその決断は、会社の未来を切り拓くための非常に重要な一歩です。
しかし、海外への道にはいくつかの見えない「壁」が存在します。言葉の壁、文化の壁、そして、多くの企業が最初につまずくことになる「ルール(規格)の壁」です。
そのルール対応の最前線に立つのが、製品の「パスポート」とも言える取扱説明書なのです。
この記事を最後までお読みいただければ、なぜ取扱説明書が重要なのか、そしてその壁を乗り越えるための具体的な道筋が見えてきます。
なぜ、取扱説明書が「最初の壁」になるのか?
「マニュアルなんて、日本語版を翻訳すればいいだけだろう?」
そう思われるかもしれません。しかし、海外向けの取扱説明書は、単なる翻訳作業とは全く異なります。そこには、大きく分けて3つの「壁」が立ちはだかっているのです。
1. 単なる「翻訳」では通用しない「文化と安全基準」の壁
日本では「言わなくても分かるだろう」「この図を見れば伝わるはず」といった、いわゆるハイコンテキストな表現が許容されることがあります。しかし、多様な文化背景を持つ人々が手にする海外向けマニュアルでは、誰が読んでも一通りにしか解釈できない、明確で直接的な表現が求められます。
とくに、安全に対する考え方は欧米と日本で大きく異なります。日本では「注意喚起」レベルのことでも、海外では具体的な危険性や回避方法まで明記しないと、メーカーの責任を問われる可能性があります。
「正しく翻訳できていること」と「安全が伝わること」は全くの別問題なのです。
2. 国や地域で全く異なる「法律・規格」の壁
これが最も厄介な壁です。例えば、欧州(EU)に製品を輸出するにはCEマーキングへの適合が法律(Regulation (EC) No 765/2008など)で義務付けられています。アメリカにはANSIという製品安全ラベルの規格があります。
これらは単なる「推奨」ではありません。製品そのものはもちろん、取扱説明書に記載すべき項目や警告の表示方法まで、法律レベルで厳格に定められているのです。この規格を満たさなければ、税関を通過できず、販売することもできません。
3. 専門知識とコストがかかるという「リソース」の壁
これらの規格をすべて自社で調査し、理解し、対応するのは、中小企業にとって大きな負担です。「担当者が本来の業務と兼任で、膨大な英文の規格書を読み解く」「そのために専門家を新たに雇うほどの余裕はない…」というのが実情ではないでしょうか。
このリソース不足こそ、多くの企業が海外展開の第一歩でつまずいてしまう最大の原因です。
多くの企業が陥る、取扱説明書対応の3つの落とし穴
落とし穴1:Google翻訳や安価な翻訳サービスに丸投げしてしまう
コストを抑えたい気持ちはよく分かります。しかし、機械翻訳や専門外の翻訳者に依頼した結果、製品の重要な技術用語が不正確に訳されたり、安全に関する微妙なニュアンスが抜け落ちてしまうケースが後を絶ちません。最悪の場合、ユーザーの誤使用による事故を引き起こし、訴訟問題に発展するリスクすらあります。
落とし穴2:「日本のマニュアルをそのまま英訳」してしまう
日本のマニュアルは、丁寧で親切な反面、情報量が多く、海外のユーザーからは「要点が分かりにくい」と評価されることがあります。海外の規格では、安全に関する警告を最優先で記載するなど、構成の順番が定められていることがほとんどです。日本向けの構成のまま単純に英訳しただけでは、規格違反となる可能性が高いのです。
落とし穴3:「とりあえず後回し」にする
製品開発や営業活動を優先し、マニュアル作成を後回しにしていませんか?いざ輸出しようという段階でマニュアルの規格違反が発覚し、出荷停止や発売延期に追い込まれるケースは少なくありません。取扱説明書は、製品開発と並行して進めるべき重要プロジェクトなのです。
「壁」を乗り越えるための具体的な進め方
では、どうすればこの壁を乗り越えられるのでしょうか。専門家に依頼するにしても、自社で進めるにしても、基本となる進め方は同じです。
ステップ1:【調査】まず、輸出先の「規格」を特定する
最初に行うべきは、自社の製品をどの国・地域に輸出したいのかを明確にし、そこで求められる規格を特定することです。
| 輸出先 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| EU 向け | CEマーキング(機械指令、低電圧指令など)の適合要件 |
| 北米向け | ANSI 規格や UL 認証の要求事項 |
情報源としては、JETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトや、現地販売代理店への確認が確実です。
ステップ2:【構成】日本のマニュアルを「海外向け」に組み直す
特定した規格で要求されている項目(安全情報、製品仕様、設置方法、廃棄方法など)を洗い出し、それに沿ってマニュアル全体の構成案を作成します。日本の取説をベースにしつつも、章立てや情報の優先順位を海外のルールに合わせて組み直す、非常に重要な工程です。
ステップ3:【執筆・翻訳】専門用語を管理し、誰が読んでも分かるように書く
設計図が完成したら、いよいよ執筆と翻訳です。ここでのポイントは、専門用語の対訳をまとめた用語集を作成し、マニュアル全体で訳語を統一すること。そして、一文を短く、誰が読んでも誤解の余地がない平易な言葉で記述することが重要です。これにより、翻訳の品質が安定し、ユーザーの誤解を防ぎます。
とはいえ、コストが心配… という場合には?
「進め方は分かった。でも、やはり専門家に頼むと費用が高いのでは…」
その懸念はごもっともです。確かに、大手のマニュアル制作会社に依頼すると、営業担当者やディレクターなど多くの人が関わるため、管理費などの間接コストが上乗せされ、料金が高額になりがちです。
当サービスでは、大手制作会社と同じ、あるいはそれ以上の実務経験を持つ専門家が、ヒアリングから納品まで一貫して担当します。余計な中間マージンや管理費がかからないため、大手と同品質のサービスを、より柔軟に、そして適正価格で提供可能です。
これは、品質を落とさずにコストを抑えたい中小企業様にとって、最も賢い選択肢の一つだと確信しています。
取扱説明書は「コスト」ではなく、未来への「投資」です
海外向けの取扱説明書対応は、面倒で費用のかかる「コスト」だと感じられるかもしれません。
しかし、適切に作られたマニュアルは、海外での無用なトラブルや訴訟リスクから会社を守り、製品の価値を正しく伝え、顧客満足度を高めてくれます。それは、貴社の海外事業を成功に導く、未来への「投資」に他なりません。
海外展開の成功は、この最初の壁をいかに賢く乗り越えるかにかかっているのです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件での法令適合性を保証するものではありません。
\当サービスでは、低コストで高品質なAI時代の取扱説明書作成サービスを提供しています。/
